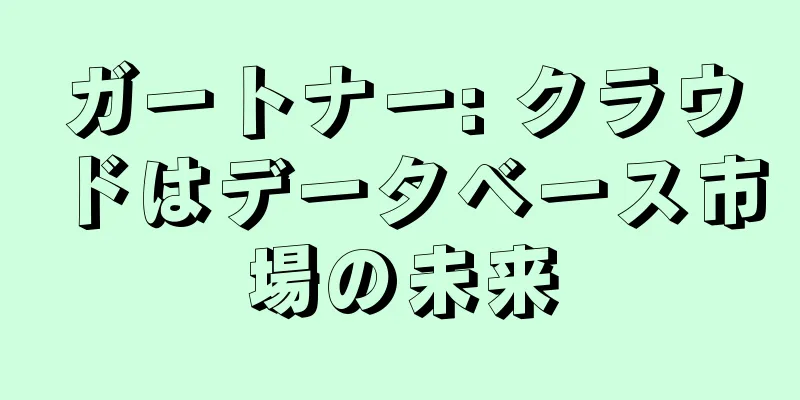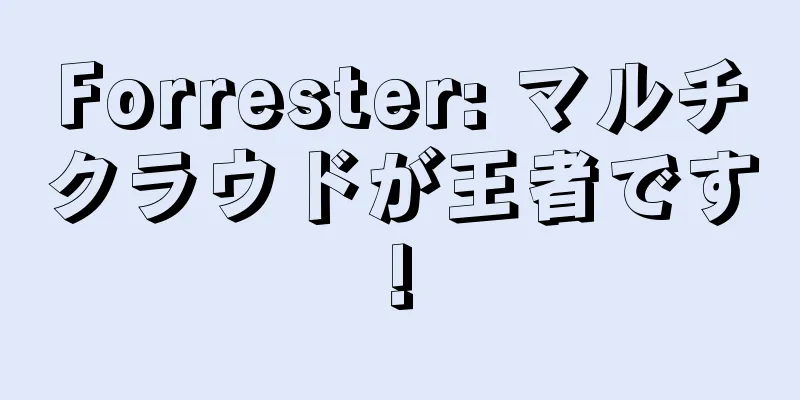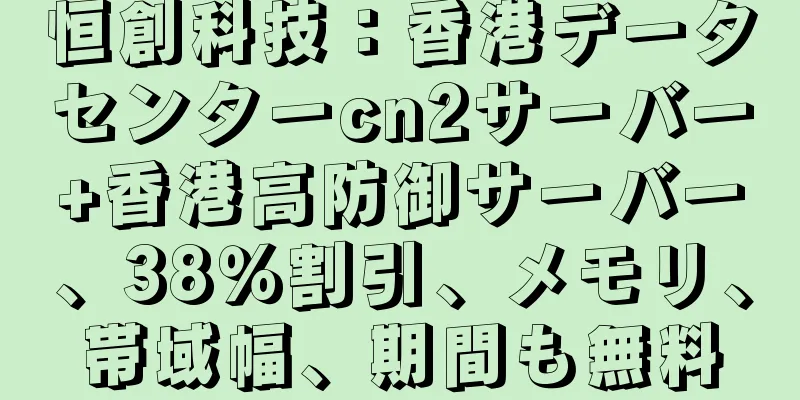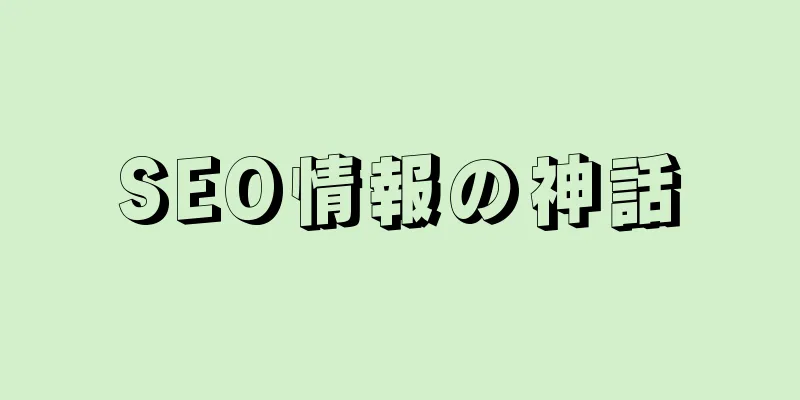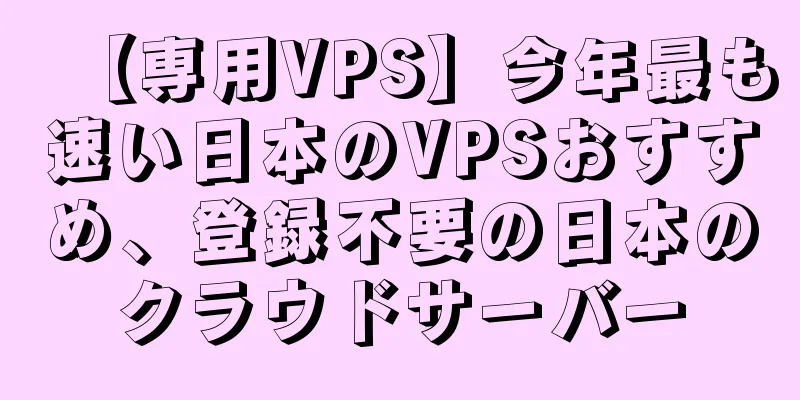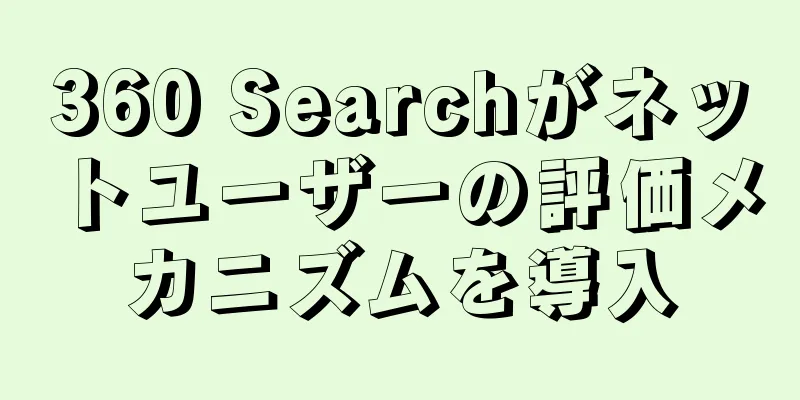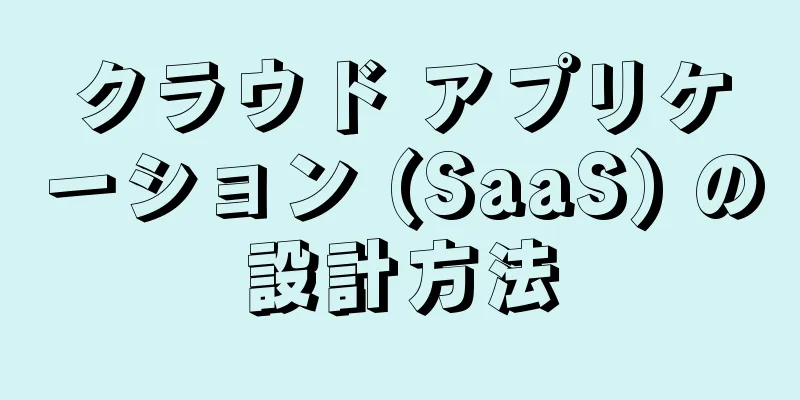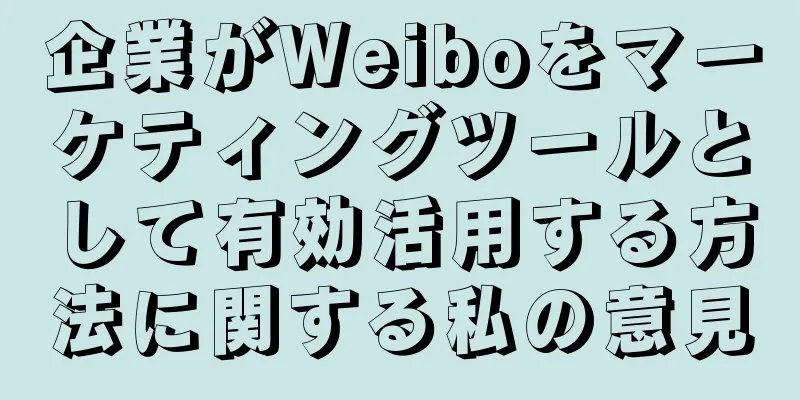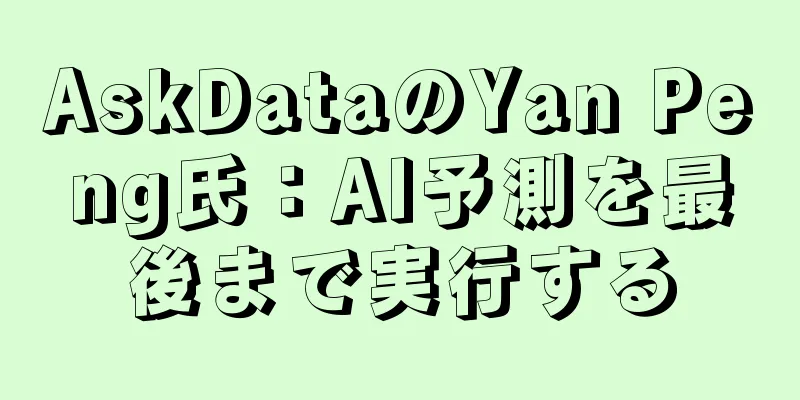B2C電子商取引はどこへ向かうのか:将来的にはC2Bモデルへと移行する
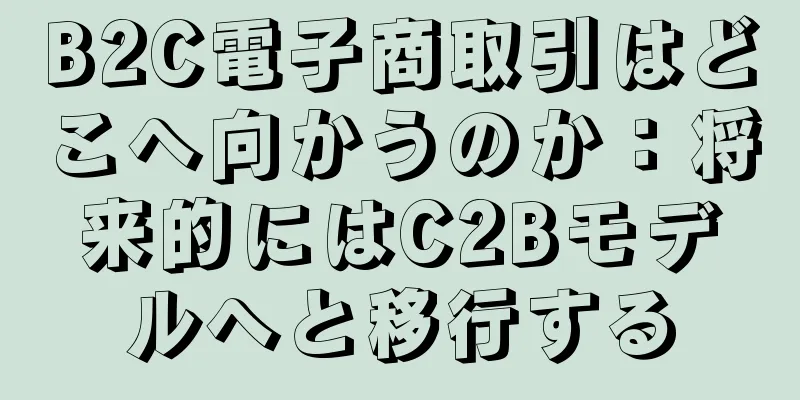
|
著者: 江 啓平 B2C電子商取引分野では、領土をめぐる競争が激化しており、天猫、JD.com、蘇寧が互いに争い、「史上最強の電子商取引価格戦争」が勃発している。この現象は、中国の電子商取引が現在「価格戦争」モデルに支配されているという現実を反映している。 この現象の背後には、あるビジネスダイナミクスがあります。中国の電子商取引における最も基本的な機械的関係は、ポニーとカートの関係です。電子商取引のポニーは取引量の5%未満を占めるのに対し、実店舗のカートは95%を占めています。中国の電子商取引では価格競争が主流であり、それはポニーとカートの相対関係によって決まる。 この関係は、2 つの側面から分析できます。1 つ目は、電子商取引のポニーが物理的な商取引の大きな荷車によってどのように制約されているかを探り、電子商取引における価格戦争の決定要因を説明することです。2 つ目は、ポニーが大きな荷車に適応し、避けられない価格戦争に巻き込まれる方法を探り、電子商取引における価格戦争の現実を説明することです。3 つ目は、ポニーが知恵を体現した新しい戦略を使用して大きな荷車を運転し、運命の必然性から逃れる方法を探ることです。価格競争から抜け出す中国の電子商取引の合理性の価値源を説明します。 B2C 電子商取引はどこへ向かうのでしょうか? Zeng Ming 氏は次のように語っています。「B2C は単なる過渡的なビジネス モデルであり、将来の真のビジネス モデルは C2B (顧客から企業へ) です。」 B2C は現実的であるから合理的であり、C2B は合理的であるから必ず現実のものとなるでしょう。 B2Cは単なる過渡的なビジネスモデルである 1. 電子商取引の発展に対する従来の制約 1) 電子商取引の惑星は物理的な星によって制御されている 強さを取引量で測ると、現在、電子商取引と実店舗の商取引の力の比較は約 5% から 95% です。 社会財の総小売売上高と比較すると、オンライン小売売上高の割合はまだ比較的低いです。商務省のデータによると、2010年の消費財小売総売上高は15兆4500億元だったが、B2Cデータはわずか1040億元で、全体のわずか0.7%を占めた。家電業界では、スカイワースはタオバオ、パイパイ、JD.comなどのオンラインチャネルと提携しているが、その売上高は全体の約4%に過ぎず、JD.comの総売上高はわずか100億元で、家電販売市場の1%未満、蘇寧電器の売上高の7分の1未満を占めている。衣料品業界では、2009年の国内衣料品市場売上高は1兆3000億元であったが、衣料品のオンライン小売売上高は衣料品小売売上高全体の3%未満を占めた。 私がこう言うのは、Tmall、JD.com、Suningの間で起こっている価格戦争に新たな説明を加えるためである。市場シェアの95%を占める実店舗での商取引で価格戦争が蔓延しているのであれば、わずか5%を占める電子商取引の「小惑星」でも当然、価格戦争が中心になるはずだ。これは、Tmall、JD.com、Suning 自体が希望するかどうかには左右されません。最も典型的な例はジャック・マー(Weibo)で、彼は常に「小さくても美しい」を主張してきましたが、中国の国情の現実に影響を受け、結局「大きくても美しい」を実現しました。 Tmall、JD.com、Suningはいずれも価格競争を繰り広げている。その理由は、一言で言えば、トップの座を争っているからだ。規模が大きいほど、より良い生活ができるのだ。 なぜそうなるのでしょうか。それは、我が国の実体商業全体が、規模拡大を追求し、価格競争を手段とし、徹底的な管理を特徴とする伝統的な流通モデルからまだ脱却できていないからです。太陽が地球を吸い込んで回転するように、電子商取引も自らの本質に反して、実体経済の法則に従って運営されています。これは、Tmall、JD.com、Suning の電子商取引企業間の価格競争の背後にある目に見えないマクロの力です。 2) 物質循環産業の重心の惑星軌道図 これは我が国の物理循環産業、重力中心の惑星軌道図を分析することで明確に確認できます。循環システム改革と循環産業発展の主な任務、支援政策、保障措置から、循環産業の95%に伝統的な農工業国としての中国の伝統的な循環遺伝子を見ることができます。 中国の流通産業を銀河に例えると、中心にある星は近代性を核としたいわゆる「現代流通システム」であり、その近代性、つまり工業化の現代的特徴は、主に物理的な業務形態(仮想業務形態ではない)に基づく国家基幹流通ネットワークに反映されている。この物理的ネットワークは、集中した都市に重点が置かれ、分散した農村地域はそれほど重視されていません。その近代化の暗黙の前提は、工業化を完了した先進国のそれとは異なります。電子商取引の助けを借りて、要素が都市から農村地域に分散的に拡散するのではなく、逆に農村地域から都市(大都市、中小都市)に要素が集まります。 逆に、タオバオプラットフォームでは、逆の世界の傾向が見られます。3、4級都市の成長率は1、2級都市の数倍であることがわかります。今後2、3年ほどで、中国の3、4級都市のタオバオでの売上高は、1、2級都市の売上高を上回るはずです。これはまさに、かつて主流から見放され、情報生産性の条件下で復活しつつある「小型化と分散化」の方向性です。 現代の 95% の流通ポジショニングは、e コマースの要件とは戦略的に異なります。流通の近代化は主に工業化の教訓を補うという低レベルの目標に位置付けられており、電子商取引は星の端にある惑星として、戦略要素以外のローカルな要素としてのみ機能し、この「半農半工業」の近代化の位置付けに奉仕し従うことができます。したがって、電子商取引は、仮想マッチメイキングの助けを借りて、技術的にリソースの物理的および空間的制限を打ち破り、都市と農村の平等な発展を実現し、流通空間で分散型、ポイントツーポイント、パーソナライズされた方法でリソースを割り当て、価格競争を特徴とする中国製のスタイルの広範な管理から脱却できたとしても、そのサイズが小さいため、銀河の中心の星になり、工業化をその周りで回らせることは困難です。電子商取引は、流通分野において、全体的な根本的観点から、Made in China モデル(つまり価格競争モデル)から脱却することができない。ここに最も深い制約がある。 中国でも流通システムの改革や流通産業の発展が頻繁に検討されているが、共通の問題は新たな現代的な位置づけの視点が欠如していることである。例えば、旧内政貿易部が出した「流通システム改革の深化と流通産業の発展促進に関する若干の意見」(内政貿易弁公室[1995]第9号)には、「流通産業の近代化の核心問題は、流通効率の向上である」という時代遅れの概念が明確に述べられている。そこで問題となるのは、曽明が指摘したように、「技術手段を用いて小売りリンクを以前より少しだけ効率化するだけでは、電子商取引の未来を誰もが見通すことは難しいだろう」ということである。なぜなら、世界の流通産業の近代化の位置づけは、もはや効率ではなく、価格競争とは逆の方向の有効性にあるからである。 なぜなら、循環システムは、効率性の向上(有効性の向上ではなく)の観点から、集中型の大規模な従来の工業化モデルに適したシンプルなシステムだからです。これは、インターネットに反する次の考え方に表れています。「国有流通会社がメインチャネルの役割を果たしたいのであれば、小規模で分散的な発展の現状を変え、組織化の程度を急速に高めなければなりません。」これは、大きいことは美しいという考えにつながり、規模の経済を実現するために価格競争を仕掛けるほど「美しい」ことであり、これを「会社の規模の管理能力を向上させる」こと、「規模と総合的な優位性を活かせる大企業グループになることを目指す」ことの要件として使用します。電子商取引が急速な発展を遂げる中で、その「重み」が5%から50%以上に増加して初めて、電子商取引は他者の周りを回る惑星から、他者が自分を中心に回る星へと変身することができるのです。 2. B2C電子商取引は価格競争を通じて伝統的な現実に適応する 1) 大きいほど美しいeコマースの価格競争の現状 現在の B2C 市場は発展の初期段階にあります。初期段階の特徴としては、電子商取引サービス企業が市場シェアをめぐって熾烈な競争を繰り広げており、規模は大きいが強くないという点が挙げられます。競争の中で生き残ることができるのは大企業だけであり、企業はさらに大きくなることを目標に競争に投資することになります。ベンチャーキャピタルの支援により、企業は人材、物流、プロモーションなどの面に多額の投資をしたいと考えています。価格競争の鍵は「大きい」ことだ。 拡大(規模拡大)と強化(利益拡大)を同時に行うことは困難です。それどころか、競争は主に利益の損失につながる方向で起こります。ベンチャーキャピタルの支援を受けて、B2C企業は価格を下げ、プロモーションを続けています。 Vanclは「1日の売上高は600万近くあるが、Vanclは損失を出しており、損失額は1億元以上に達した」と述べた。JD.comの粗利益率は10%を超えず、GomeとSuningの粗利益率はどちらも17%前後である。 電子商取引の本当の利点は、効率性(つまり、複雑さや感度に対する効率性)の向上にあります。環境が複雑で多様であればあるほど、電子商取引の利点は大きくなります。 「大きいことは美しい」という原則を単に追求するだけでは、必ずしも電子商取引が物理的な商取引よりも効率的になるということではありません。 2) B2Cは現実の4つの側面に適応する 電子商取引の価格戦争は、発展途上国の状況下での電子商取引の現実への適応を反映しています。 適応の第一の側面は価格競争です。共同購入の増加は、電子商取引が実店舗での商取引に適応しつつあることの現れです。実店舗での商取引の中間リンクにおける莫大な利益は、低価格で競争する豊富なユーザーリソースを備えた電子商取引ウェブサイトの繁栄を誘発しました。オンライン販売モデルにおけるイノベーションの最も活発な分野は、差別化やパーソナライゼーションではなく、共同購入、期間限定購入、フラッシュセール、代理購入など、さまざまな形式の価格競争であり、多くのネットユーザーの注目を集め、ウェブサイトのマーケティング力と売上を拡大しました。価格競争により、電子商取引のイノベーションは拡大へと移行しました。例えば、百貨店は売上を伸ばし、リスク耐性を高めるための効果的な手段として活用されています。例えば、当堂の書籍販売シェアはどんどん低下していますが、百貨店展開により、現在は150万点の商品を揃えています。 適応の2番目の現れはコスト競争です。電子商取引の副産物としてのコスト優位性が最初に発揮されます。例えば、一部の電化製品メーカーの在庫回転率は50日です。実店舗の在庫回転率が50日であるのに対し、JD.comの在庫回転率はわずか11日であるため、Suning、Gome、Walmart、Intime Department Store、Carrefourなどの伝統的な小売企業は、すべてB2C分野に参入しています。それどころか、従来の条件の制限により、電子商取引の差別化と多様化の利点が十分に活用されていません。 適応の 3 番目の現れはチャネルであり、電子商取引ではオンライン モードとオフライン モードの組み合わせが広く採用されています。たとえば、マクリンズは、実店舗ビジネスを第一級、第二級、第三級都市に拡大するために、400 を超えるフランチャイズ店舗を誘致しました。 適応の 4 番目の現れは、自社構築のロジスティクスです。実体ビジネスが未発達で、サードパーティロジスティクスが十分に発達していないため、電子商取引プラットフォーム企業の発展はしばしば制限されています。一部の B2C 企業は、多額の費用をかけて独自の物流を構築する必要があります。近年、JD.comは融資資金の70%を倉庫・物流建設に充て、北京を含む5つの都市で1級物流センターの配置を完了した。現在、同社の3級物流システムは全国50都市をカバーしている。 これら4つの適応から、電子商取引は独自の強みで伝統的なビジネスを牽引しているのではなく、物理的なビジネスよりもコストが低いという相対的な弱点を利用して伝統的なビジネスを牽引し、物理的なビジネスの産業化の未完了の教訓を補っていることがわかります。その結果、B2C プラットフォーム企業間で深刻な同質競争が生じ、製品カテゴリやビジネス モデルの類似性、差別化された競争の欠如という形で現れています。 従来の重力から脱却する B2C 電子商取引の進化の方向性: ビッグデータ時代のC2Bは小さくて美しい 伝統的な商業は強力ではあるが、克服できない欠点もある。例えば、商務省研究院消費経済研究部の趙平副部長は「社会が創出した富の大部分は流通経路で消費されており、中国経済に大きな負担を課し、経済構造転換を妨げている。同時に、物価水準を押し上げ、消費の解放を妨げている」と指摘した。 しかし、インターネット時代においては、これは避けられないことではありません。電子商取引は必ずしも価格競争の道を進む必要はなく、現実に適応しながらも、自らの合理性を発揮することもできる。電子商取引のさらなる発展に伴い、小ロット・多品種の電子商取引が登場するでしょう。 Amazon は 3,000 万点以上の商品を販売していますが、JD.com は 10 万点の商品しか販売していません。中国市場は小さく美しいため、大きな可能性を秘めています。電子商取引が独自の特性を十分に発揮することができれば、従来の物理的なビジネスの重圧から解放されることができます。この方向で考えると、B2C にとって最も根本的な解決策は C2B になります。アリババ(微博)に代表される中国の電子商取引サービス企業は、この新たな方向性を模索している。 1. 将来の電子商取引の真のビジネスモデルはC2Bである B2C 自体は、真の電子商取引への移行形態にすぎません。従来のビジネスモデルの重力に惹かれる主な理由は、従来のビジネスと同様に、B を中心とし、B から始まり、最終的に C に到達することです。電子商取引の違いは、根本的に言えば、BからCへの単純な効率化ではなく、Cを核として、CからBへとBとCの立場を根本的に逆転させ、「生産と消費の逆転」(生産者と消費者の関係の逆転)を実現することです。 2. C2Bバリューチェーンにおける「生産と消費の逆転」の4つの主要なリンク 1) バリューチェーンの第一の原動力:情報の流れの源としての消費者 曽明氏は、B2C標準モデルは伝統的な工業経済時代の運営モデルであると考えています。今後、インターネットの発展に伴い、消費者の声はますます強くなり、将来のバリューチェーンの第一の原動力はメーカーではなく消費者から来るでしょう。 B2C はあくまでも過渡的なビジネスモデルであり、将来の電子商取引の真のモデルは C2B にあります。 「今後はビジネスモデルのカスタマイズが主流になるでしょう。パーソナライズされたニーズ、多品種、小ロット、迅速な対応、プラットフォームベースのコラボレーションが必要です。これが私たちが見通せる未来です。」 C2B モデルのフロントエンド (顧客情報収集側) における鍵は、Web 2.0 集約技術を通じて複雑かつ多様な消費者を集約し、従来不利とされてきた消費者の立場を逆転させることです。共同購入は、ある意味では望ましい。それは、生産と消費の逆転の主要な形態である。実際、SNS も検索エンジンも、消費者の行動を経済プロセスの出発点として利用し、最終的には生産者の生産と消費の逆転ビジネスモデルにつながります。 B2Cの観点から見ると、経済プロセスの出発点に注文を配置することで、人と注文の統合を実現すると理解できます。 2) バリューチェーンの2番目のリンク:情報フローの再編成 - 大規模な非構造化データ処理業界 最初の原動力の問題が解決されると、次に私たちが直面するのは、消費者行動に関する膨大なデータの処理です。ビッグデータ時代の電子商取引では、膨大な量の非構造化データを処理するためにクラウド コンピューティングを使用する必要があります。 データ処理産業の付加価値化後、データフローは生産と消費の逆転という新たな方向を辿り、資本フローと物流を統合する役割を果たし、最終的に業務フローの再編を実現します。 3) バリューチェーンの3番目のリンク:ビジネスフローの再編成 - 広告、チャネル、サプライチェーンの統合 曽明氏の予測によれば、ビジネスフローの再編では、広告、チャネル、サプライチェーンが順に変化するだろう。彼は、B2C標準モデルは、伝統的な工業経済時代の大規模、組立ライン、標準化、低コストの運営モデルであり、在庫はその自然なモデルでは避けられない致命的なポイントであると考えています。在庫があるということは、人と注文が一体化できないということです。業務フローを整理し、在庫をなくすことで、人と注文の一体化を実現することが本質です。 最初に変化したのは広告市場です。Google は成果報酬型 (p4p) のビジネス モデルを通じて、従来の広告ビジネス モデルを根本的に変えました。広告は、もともとブランディングに傾倒していた価値提案から、精密なマーケティング プラットフォームへと移行しました。商取引の電子化における第 2 段階は、実際には小売プラットフォームのネットワーク化です。次のステップは、サプライチェーンのリアルタイムコラボレーションプラットフォームです。言い換えれば、電子商取引がオンライン小売からサプライチェーンのリアルタイムコラボレーションに移行して初めて、バリューチェーンのあらゆるリンクがインターネット上で真に実現可能になります。もはやオンラインとオフラインに隔てられた孤立した島ではありません。 曽明氏によると、この3つの流れが繋がると、まさにビッグデータの時代となるという。ビッグデータが真にサポートするビジネス モデルは、B2C ではなく C2B です。なぜなら、本当に多くの消費者向けに大規模にカスタマイズしたいのであれば、産業チェーンを再構築する必要があるからです。中間データのディープマイニングとマッチング精度の幾何学的向上は、このビジネスモデルに必要なインフラストラクチャです。これが私たちが見ることができる未来です。 4) バリューチェーンの4番目のリンク: 注文に基づくカスタマイズ、人間中心、単一顧客の統合 「rendanheyi」の「ren」は生産者、「dan」は消費者を指します。最終的には、あらゆる業種の企業を指すBが受注生産を実現することになる。消費者の情報から生み出される指令に応じて、社会全体で資源が配分され、生産が組織化されます。 生産と消費の逆転が起こる前は、ほとんどのメーカーがタオバオの売り手に10万個や50万個の注文をすることはできたが、1個どころか500個だけをタオバオの売り手に注文することは不可能だった。生産と消費が逆転する状況下で、柔軟な生産能力を持つサプライヤーは、多品種、小ロット、迅速な対応で生産ニーズを満たすことができます。従来のサプライチェーンの回転率は基本的に約 28 日ですが、インターネットでは将来的には 7 日、あるいはそれよりも短い期間が必要になります。現在、ハイアールの生産・製造においては、生産と消費の逆転、人と人の融合が十分に実現されています。 B2C 電子商取引はどこへ向かうのでしょうか? 将来は、これまでの B2C の単なる継続ではなく、C2B への飛躍と反転となるかもしれません。 原題: B2C 電子商取引はどこへ向かうのか: 将来的には C2B モデルへと移行する キーワード: B2C、電子商取引、どこへ行くか、C2B、モデル変更、著者、Jiang Qiping、ウェブマスター、ウェブサイト、ウェブサイトのプロモーション、収益化 |
>>: 電子商取引のサンプル: ユニークな食品電子商取引ウェブサイト
推薦する
運用上の考え方を変えることの重要性の例
Baidu の最近のアルゴリズム更新は、多くのウェブマスターを落胆させています。ウェブサイトをより良...
百度のアルゴリズムは「無期限に変更」ウェブマスターの対応が鍵
数日前、Baidu 検索で突然、一時的なエラーが発生しました。このエラーは長くは続きませんでしたが、...
インターネット大手がエンタープライズ市場に注目する理由
インターネット市場を最も単純かつ大まかに区分すると、消費者市場と企業市場に大別できます。前者は個人ユ...
4月の第1週には、.COMドメイン名が約9万件増加して1位となり、.AISAは2万5千件減少した。
IDC Review Network (idcps.com) は 4 月 10 日に次のように報告し...
インターネット大手が野菜販売業者の生計を奪っている
1つ今年、「コミュニティグループ購入」というビジネスモデルがますます普及し、コミュニティグループ購入...
#ブラックフライデー#: stablehost - 仮想ホストが25%オフ/リセラーが60%オフ/VPS/3データセンターが60%オフ
Stablehost の毎年恒例のブラックフライデー プロモーションが正式に発表され、新規顧客向けと...
マイクロソフト リサーチ アジア インテリジェント オペレーション: クラウド サービスのインテリジェントな推進力
この疫病は人々の生産や生活の仕方を変えました。共同作業、リモートワーク、オンライン教育などのシナリオ...
SaaS 時代の未来を予測する |第8回クラウドコンピューティングアプリケーションフォーラムが開催中です
過ぎ去ろうとしている2017年、SaaS業界は穏やかに見えますが、実は暗流があります。過去 1 年間...
Bilibiliでの商品のライブストリーミングは誤報ですか?
「愛のために発電する」か「トラフィックを収益化する」か、 B局はライブストリーミング販売の選択に迷う...
pq.hostingはどうですか? 10Gbps帯域幅のアイルランドVPSの簡単なレビュー
pq.hosting には、アイルランドのデータセンターを提供するアイルランドの VPS 事業を含め...
テンセント第3四半期財務報告:テンセントカンファレンスのユーザーが1億人を突破、クラウド事業がベンチマークを加速
テンセントは11月12日、2020年第3四半期の業績報告書を発表した。 2020年第3四半期、同社の...
品質を向上させ、入札を簡単にマスターするためのクリエイティブ最適化のコツ
品質は、検索エンジンマーケティング (SEM) において非常に重要な要素です。アカウント全体の最適化...
訪問者分析に基づくサイト広告レイアウトに関すること
最近では、多くのサイトが広告のクリック率を高めるためにあらゆる手段を講じています。たとえば、「クリッ...
cloudsilk: ドイツ本土のプレミアム最適化 BGP クラウド サーバーが販売中、10% 割引、月額 35 元から
新しいドイツのクラウド サーバーの立ち上げを記念して、CloudSilk (Baisi Networ...
Google の急成長の暴露: Nokia を破った後、Microsoft が次のターゲットになるのか?
Googleは設立以来、魔法に満ちたハイテク企業であり続けています。Googleの発展の歴史を見ると...